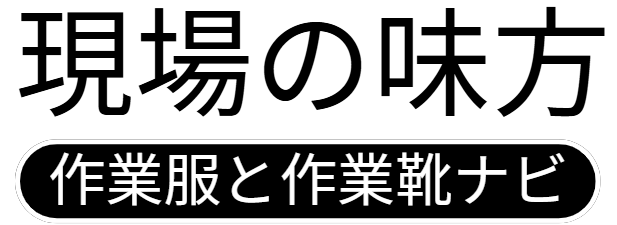支えてきたのに、継がせてもらえない。そんな理不尽、ありませんか?
はじめに
「二代目が会社を潰す」——よく耳にする言葉ですが、実際には“継がせてもらえない”という逆のパターンも少なくありません。
若い頃から現場に立ち、会社の業績を支えてきたにもかかわらず、
「まだ任せられない」
「お前には無理だ」
「自分がいないと会社は回らない!」
と、親がいつまでも経営を手放さない。
そんな悩みを抱える二代目候補は全国に数多く存在しています。
この記事では、継がせてもらえない問題の背景と、円満に事業承継を進めるための具体策を解説します。
この記事を読むことで、親世代との対話の糸口が見え、現実的な承継の道筋を描けるようになります。
なぜ親は譲らないのか?その背景と心理
親の不安と執着が原因
結論から言えば、**継がせない最大の原因は、親の「不安」と「執着心」**です。
- 自分がいなければ会社が回らないという思い込み
- 息子に任せて失敗されたら困るという恐れ
- 若さや経験不足を理由に信用しきれない
しかし、実際には次のような状況が現場では起きています:
- 息子が20代から現場に立ち、営業・管理業務を一手に担っている
- 業績を回復させた実績がある
- 従業員の信頼も厚く、実質的な経営者として機能している
- 一方で、親は資格も持たず、実務にも関与せず、通帳だけを握っている
- 息子は低賃金でフル稼働している
- 親は私情で従業員を解雇し、信頼を失っている
- 親自身に実績がなく、息子に生活を支えられている自覚がない
- 「俺の会社だ」と言い張り、社内外で孤立している
このような状態では、本来なら評価されるべき後継者が孤立し、精神的にも追い込まれることになります。
実例で見る:継がせないことで会社が傾くまで
身近で起きた継承トラブル
筆者の知人の話です。従業員10人程度の小さな建設会社で、息子が20代から現場を支え、20代後半には受注管理もこなしていました。
ところが父親は「任せられない」の一点張りで、銀行対応のみ自分で行っていました。実際には資格も経験も乏しく、従業員の信頼もなかったにもかかわらず、「俺の会社だ」と譲る姿勢は一切なし。
息子は50代を目前に限界を感じて退職。彼を信頼していたスタッフも辞め、独立して新会社を設立。
結果、父親は人材と信用を同時に失い、会社は急激に縮小。廃業となりました。
製造業の失敗事例
ある製造業の会社では、30代の息子が10年以上実務を支えていましたが、父親は代表取締役の座を譲らず、意思決定も全て掌握。
息子は「信用されていない」と感じ独立。後継者を失った会社では人材も次々に離職し、業績は大幅に悪化。
“継がせない”ことが、会社の存続を危うくする結果を招いたのです。
円満な事業承継に向けた3つのステップ
1. 感情を整理し、対話の場をつくる
親子経営は感情の対立を招きがち。冷静に対話できる場を設けましょう。
第三者(弁護士・信頼できる経営者など)を交えることで、感情を整理しやすくなります。
2. 承継計画を「見える化」する
「そのうち任せる」では曖昧すぎます。いつ、誰が、何を、どのように引き継ぐのかをスケジュールとして明文化しましょう。
書面での共有がポイントです。
3. 役割と報酬のルールを明確にする
現経営者と後継者、それぞれの役割・報酬・責任範囲を文書で定め、あいまいさを排除します。
こうすることで社内の混乱も抑えられます。
結論:早期の準備と覚悟が明暗を分ける
信頼と準備こそが事業承継の鍵です。親子だからこそ、言いづらいこともあるでしょう。
しかし、**「譲る覚悟」と「継ぐ覚悟」**を持ち、早期から話し合いと計画に着手することで、円満なバトンタッチが実現できます。
まとめ
- 継がせてもらえないトラブルは中小企業で増加中
- 原因は親の不安・執着・自覚のなさ
- 息子が実質経営していても、評価されないことが多い
- 結果、後継者が離脱し、会社が傾くケースも
- 解決には「対話・計画・役割の明確化」が不可欠
- 早い段階からの行動が、会社の未来を守ります
- 親子であっても線引きを明確にし、優しさに頼らない体制を
公式リンク
行動のすすめ
継ぐ覚悟、できていますか?
そして、譲る覚悟はありますか?
いまこそ、親子で「未来」を真剣に語るときです。
感情ではなく、仕組みと行動で会社を守りましょう。